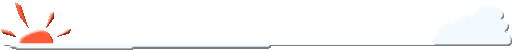
ハイブリッド・ティ(HT)とつるバラ
の年間管理
| 1月 |
根は活動しない。大苗の植え付けや移植の時期。元肥の最適期。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 芽が休眠中につき水やりは必要ありません。 ただし、この冬に新しく植え付けた大苗は植え付け後1週間経っても雨が降らなければ15㍑程水をやります。 |
| 鉢植え | 晴天が続けば休眠中でも水は与えます。 7〜10日に1回、午前10時ぐらいまでに鉢底から水が流れ出るくらいに。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 元肥を12/中〜1月(最適期)にします。 有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各75g混合した計300gを株周辺に撒いて、深さ10cm程中耕します。 (化成肥料を使う場合は、土の性質にもよりますが、標準的な量はマグァンプKなどの緩効性化成肥料(N-P-K=6-40-6)で、200g程度。 ただし、化成肥料は段々に土をやせさせるので、極力、有機質肥料を使いましょう) |
| 鉢植え | 土替えの際に、元肥をします。 上記有機質の肥料を10号鉢ならスプーン(大)3杯(45g程度)を鉢の縁3箇所に施します。 (マグァンプKなど緩効性化成肥料N-P-K=6-40-6)で代用してもいいでしょう) |
| 3)石灰硫黄合剤 (病虫害対策) |
うどんこ病、黒点病の胞子、害虫の卵を殺すために、最高気温4℃以下の日を選んで、石灰硫黄合剤の8〜10倍液に展着剤10000倍で加えたものを散布もしくは塗布します。特に、地表から地上20cmのところを丁寧にかけます。 最低気温が7℃以上のときに散布すると葉が縮れる薬害が発生る恐れがあるので、注意。 |
| 2月 | 冬剪定の最適期。大苗の植え付け、植え替え、移植は2月中旬までに済ませましょう。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 1月同様、水やりは必要ありません。 |
| 鉢植え | 晴天が続けば7〜10日に1回。 |
| 2)施肥 | 元肥を施してあれば必要ありません。まだ、元肥をしていない場合は、上旬までに済ませましょう。 |
| 3)HTの冬剪定 |
2月(最適期)に入ったら芽が動く前の2/10までに剪定を済ませましょう。 |
| 3月 | 芽が伸び始める。芽かきを忘れないようにしましょう。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 晴天が続いたら1週間に1回、15㍑。 マルチングしていなければ株元にピートモス(2号)などを厚さ2cmぐらい敷き、乾燥防止、雨水による土の跳ね返りよる病気予防をしておきます。 |
| 鉢植え | 晴天が続いたら3日に1回、鉢底から水が流れるくらい。 新芽の先がしおれていたり、蕾が首をたれていたら水不足です。直ぐに水やりをしましょう。1時間もしたら治ります。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 既に元肥を施してあれば必要ありません。 |
| 鉢植え | 鉢植えの場合、一度に多量の肥料をやるわけにはいかないので、元肥を施していても必要量が足りない恐れがあります。今月から蕾が色つくまでの間、7日から10日に1回、液体肥料(N-P-K=6-10-5)の1000倍液を水やり代わりに与えた方がいいでしょう。 |
| 3)芽かき | 今月から4月にかけて元気のよい枝の先には1箇所から3本、芽が出るので、真中の芽を残してわき芽をかきとります。 また、枝の下のほうにあり日影になるような芽、貧弱な芽も、養分を消費するので、摘み取ります。 |
| 4)病気・虫害対策 | 冬の間に石灰硫黄合剤が散布してあれば3月中旬までは、病気はまず発生しません。 病気・虫害対策の基本は早期発見・駆除です。私は特に、新芽の先のところを常時、仔細に観察し、新芽の先を枯らすゾウムシや葉を食い荒らす蛾の幼虫、新芽の先に群がるアブラムシを除去しています。 中旬になるとアブラムシやヨトウガの幼虫がみられます。気温が18℃を超す下旬には、うどんこ病が発生することがあります。 スミチオンやオルトランにトリフミンを加え、展着剤を入れて予防散布してください。 3月は新芽が柔らかいため、薬害に注意し、かけすぎたり、葉に近かづけ過ぎたりしないようにしてください。 私は、中旬頃から、薬剤の代わりに、人体に無害のバイオアクト(ニームオイルをベースとした天然性害虫対策及び植物成長促進剤)1000倍液とノースキトンL(キトサン入り天然木酢液500倍液とを混合し、10日に1回、葉面散布して予防しています。これで結構、効果があります。 万一、病虫害発生の場合は、市販のベニカXスプレーなどの薬剤を被害部及びその周辺に散布しています。 |
| 4月 | 月末には蕾が見えるものあり。春苗の植え付けの最適期。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 晴天が続いたら1週間に1回、15㍑。 新しく植え付けた春苗には植え付け後1週間経っても雨が降らなければ15㍑与えます。 |
| 鉢植え | 通常、3日に1回。ただし、鉢土が乾き、夕方になっても新芽の先がしおれたり、蕾の首がたれているようならるようなら、水不足です。直ぐに水を与えましょう。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 枝の伸びが悪いなど生育が今ひとつなどの場合、上旬と中旬に、液体肥料(N-P-K=6-10-5)の1000倍液を2〜3㍑、水やり代わりに与えます。 |
| 鉢植え | 鉢植えの場合は肥料不足となる恐れがありますので、3月同様、蕾が色つくまでの間、7〜10日に1回、液体肥料(N-P-K=6- 10-5)の1000倍液を水やり代わりに与えた方が株のためにはいいでしょう。 |
| 3)HTの芽かき | 3月に続き、枝の下の方で葉は展開しても上には伸びてこない芽や株の内側の日が当たらないところで伸びた枝葉は10cmぐらいになるまでにつけ根からかきとってしまいます。 |
| 4)HTのブラインド 処理 |
枝の先に蕾が付かなかった枝(ブラインド)は5枚葉(本葉)を3枚ぐらいつけて切ります。残した葉に基部からよい芽が伸び出します。 |
| 5)HTのわき蕾摘み | 花を大きく咲かせるために、蕾がアズキ大になったら中央の一つを残してわきの蕾を取ります。花が少し小さくなっても長く楽しみたい場合は、3個ぐらい蕾をのこすとよいでしょう。 |
| 6)台芽かき | たまに、根際から、台木のノイバラの芽が伸びてくることがあります。上部の枝を枯れさせてしまうことがありますので、生え際からかきとります。 |
| 7)病虫害対策 | 4月は病虫害の予防に特に重要な時期です。 3月同様、特に新芽の先にアブラムシ、ゾウムシなどがつき、新芽を駄目にしてしまいますので、よく観察し、対処しましょう。 害虫は新芽に群がるアブラムシや、新芽を食べるヨトウムシ、葉を糸でつづって中を食害するハマキムシ、若い蕾や新芽に産卵して黒く枯らすゾウムシなどが発生します。 中旬以降の暖かい日には、バラキクバチが太い茎に産卵して先端をしおれさせます。茎の中に産卵しているので、健全な葉を2枚つけて、被害部を切り捨てましょう。 3月同様、スミチオンかオルトランにトリフミン、ダコニールを加え、展着剤を入れて、2週間に1回、散布してください。これで、アブラムシやうどんこ病、黒点病などを防除できます。 私は、下旬から、薬剤の代わりに、人体に無害のバイオアクト(ニームオイルをベースとした天然性害虫対策及び植物成長促進剤1000倍液とノースキトンL(キトサン入り天然木酢液)500倍液とを混合し、10日に1回、葉面散布して予防しています。 そして、病虫害発生の場合は、ベニカXスプレーなどの薬剤を被害部及びその周辺に散布しています。これで結構効果があります。 |
| 5月 | 開花月。二番花のために花後の枝を上手に切り、追肥を忘れないように。元気な木はシュートが出始める。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 開花期は水を欲しがるので、乾いたら毎日。蕾があれば週2〜3回、15㍑以上水をやると花弁が伸びて花形が整います。 新しく植え付けた春苗には、1週間経っても雨が降らなければ、15㍑程度の水を与えます。 |
| 鉢植え | 今月から晴天が続けば、毎日必要となります。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 開花前は、花形が乱れるので、やりません。 一番花が終わったらお礼肥として追肥します。 肥料は有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各100gを混合した計400g程度与えます。 |
| 鉢植え | 蕾が色づくまでの間、液体肥料(N-P-K=6-10-5)の1000倍液を10日に1回やった方がいいでしょうが、生育状況がよければやらなくてもいいでしょう。 一番花が終わったらお礼肥として追肥します。 肥料は有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各同量混合したものを10号鉢ならスプーン(大)6杯(100g程度)を鉢の縁3箇所に置きます。 (化成肥料で済ます場合は、化成肥料(N-P-K=10−10-10など)を10号鉢なら10粒を鉢の縁に置きます) |
| 3)HTの花がら切り | 一番花が散り始めたら5枚葉を2〜3枚つけて5枚葉の上5mm〜1cmのところを切ります。ただし、若い木や生育の悪い木の場合は、一番上の5枚葉の上で切り、葉の数を少しでも残して生育を助けます。 なお、切り花は花弁が4〜5枚開いてから枝に必ず2〜3枚の5枚葉を残して早期に切ります。1〜4時間ぐらい花首まで水に入れて水揚げすると生けてからしおれません。 |
| 4)つるバラの花がら 切りと整枝 |
花が終わったら5枚葉を2〜3枚残して、その上5〜10㎜のところを芽の角度に合わせて斜めに切ります。 その他、①大輪系の場合、3年以上経った古い枝は根元から切り落とし、新しい枝を残すようにする。(中小輪系は古い枝のも花をつけるので、無理に切る必要はない)②根元から比較的近いところから出た枝(サイドシュート)が出た場合、その先の主幹枝を切り取る。③花を2回咲かせて枝は根元から切り落とす。④残した枝の全ての細い枝先を20〜30cm切り詰める。③今年根元から伸びた枝(ベーサルシュートやサイドシュートは切らずにそのまま伸ばし、枝が折れないようにシュロ縄で支柱に結わえる。 |
| 5)HTのシュート (根際から出る 太い枝)の処理 |
元気な株では下旬になると株元から太い枝(シュート)が出ます。シュート先端に小さな蕾がみえたら(長さが40cmくらいに伸びたとき)、先端を7〜8cm、5枚葉の直ぐ下で折り取ります。 |
| 6)つるバラのシュー ト(根際から出る 太い枝)の処理 |
根元から新しく太い枝(シュート)が出てきます。この枝から来年以降、花が咲きますので、折れないように結わえて育てます。 |
| 7)病虫害対策 | 雨の多い年はうどんこ病の発生が激しくなります。 4月同様、薬剤散布して対処しましょう。 黒点病は薬剤では治らないので、病気の葉は地面に落ちないよう摘み取ります。 私は基本的には薬剤の散布はしませんが、前月同様、薬剤の予防散布の代わりに、人体に無害のバイオアクト(ニームオイルをベースとした天然性害虫対策及び植物成長促進剤)の1000倍液とノースキトンL(キトサン入り天然木酢液)500倍液とを混合し、10日に1回、葉面散布しています。これで結構、効果大です。 万一、病虫害発生の場合は、市販のベニカXスプレーなどの薬剤を被害部及びその周辺にスプレーしています。 |
| 6月 | 1年で最も成長する月で、株元からは太いシュートが伸びだす。月末頃には二番花が咲き始める。ただし、病虫害は多発の時期 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 今月は適度に雨が降るので、やりませんが、晴天が続き乾いたら与える。 10日以上晴天が続いたら水を与えた方が枝やシュート(根際から出る太い枝)の育ちがよくなります。 |
| 鉢植え | 晴天続きであれば毎日。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 一番花が終わったら、お礼肥として追肥をします。(5月、既に施肥していれば必要ありません) 肥料は有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各100g混合した計400g程度与えます。 |
| 鉢植え | 一番花が終わったら、お礼肥として追肥をします。(5月、施肥していれば必要ありません) 肥料は有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各同量混合したものをスプーン(大)2〜3杯(100g程度)を鉢の縁3箇所に置きます。 (化成肥料を使う場合は化成肥料(N-P-K=10-10-10)を10号鉢なら10粒を鉢の縁に置きます) |
| 3)HTの花がら切り | 5枚葉を2〜3枚つけて、その下5枚葉の上5mm〜1cmのところを切ります。 ただし、若い木や生育の悪い木の場合は、一番上の5枚葉の上で切り、葉の数を少しでも残して生育を助けます。 |
| 4)つるバラの花がら 切り |
花が終わったら葉を1枚ぐらいつけて花の直ぐ下を切ります。 ただし、秋に実を鑑賞する品種はそのまま残します。 |
| 5)HTのシュ−ト (根際から出る 太い枝)の処理 |
元気な株では5月下旬ぐらいから株元からシュートが出ます。シュート先端に小さな蕾がみえたら(長さが40cmくらいに伸びたとき)、先端を7〜8cm、5枚葉の直ぐ下で折り取ります。 |
| 6)つるバラのシュ ート(根際から 出る太い枝)の 処理 |
根際から新しく太い枝(シュート)が出てきます。この枝から来年以降、花が咲きますので、折れないように結わえて育てます。 |
| 7)病虫害対策 | 雨とともに黒点病やうどんこ病がひどくなり、花や蕾に灰色カビ病が出ます。 5月同様、週1回か、雨の合間に薬剤を予防散布します。 急に早茎が黄変し、落葉することがあります。がん腫病が根の部分に広がったり、カミキリムシが根際を食害するのが原因ですので、根際をよく調べて薬剤で処理します。 アブラムシ、クロケシツブチョッキリ(ゾウムシ)、バラキクバチなどが発生します。スミチオンなどの薬剤で退治します。 私は薬剤の予防散布に代えて、人体に無害のバイオアクト(ニームオイルをベースとした天然性害虫対策及び植物成長促進剤)の1000倍液とノースキトンL(キトサン入り天然木酢液)500倍液とを混合し、10日に1回、葉面散布しています。 そして、病虫害発生の場合は、ベニカXスプレーなどの薬剤を被害部及びその周辺にスプレーしています。 |
| 7月 | 水切れ、肥料切れをさせず、葉を少しでも多く木につけたままにすることが肝要。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 梅雨明けになると気温が上がり、乾燥するので、晴天が続けば2〜3日おきに10〜15㍑与えます。 |
| 鉢植え | 晴天であれば毎日。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 二番花が終わったら一番花と同様にお礼肥として追肥をします。 肥料は有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各100g混合した計400g程度与えます。 |
| 鉢植え | 二番花が終わったら、一番花と同様、お礼肥を追肥します。 肥料は有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各同量混合したものをスプーン(大)2〜3杯(100g程度)を鉢の縁3箇所に置きます。 (化成肥料で済ます場合は、化成肥料(N-P-K=10-10-10)を10号鉢なら10粒を鉢の縁に置きます) |
| 3)HTの花がら (二番花)切り |
二番花が終わり次第、5枚葉を2〜3枚つけてその下の外側にある5枚葉の上5㎜〜1cmのところを切ります。 |
| 4)HTのシュ−ト (根際から出る 太い枝)の処理 |
元気な株では5月下旬ぐらいから株元からシュートが出ます。シュート先端に小さな蕾がみえたら(長さが40cmくらいに伸びたとき)、先端を7〜8cm、5枚葉の直ぐ下で折り取ります。 株の途中から出る太い枝(サブシュートもしくはサッカー)には余りよい花が咲かないので、シュートと同様に先端を摘んでわき枝で花を咲かせるようにします。 |
| 5)つるバラのシュ ート(根際から 出る太い枝)の 処理 |
このシュートからは今年、花が咲きません。来年以降、花が咲く枝ですので、折れないように結わえて大切に育てましょう。 |
| 6)摘蕾 | 3番花の蕾は株の生育を助けるため摘蕾します。 |
| 6)病気害虫対策 | 梅雨が長引くと黒点病やうどんこ病が多発。 害虫はゴマダラカマキリが産卵のため飛んできて枝の表皮を食べて枯らします。幼虫のいる株は根際の穴からキノクズのような虫ふんを出すので、発見は容易です。穴に殺虫剤を吹き込んで殺します。コガネムシは蕾や浜や新芽を食べるので、捕殺します。 梅雨明けとともにハダニが広がるので、ニッソランVやダニトロンフロアンブルの1000倍で退治。 |
| 8月 | 高温と乾燥のため露地植えにも水やりは必要。秋剪定の適期で、葉をなるべく多く残して切りましょう。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 晴天が続いたら毎日、大型のバケツ1杯(15㍑)与えます。 |
| 鉢植え | 晴天であれば毎日。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 秋花のために下旬に化成肥料(N-P-K=10-10-10)を20粒施します。 (7月に施肥していない場合は、有機質肥料300g程でも可) |
| 鉢植え | 秋花のために下旬に化成肥料(N-P-K=10-10-10)を10号鉢なら10粒施します。 |
| 3)病虫害対策 | 30℃を超すと黒点病やうどんこ病の発生は下火になりますが、雨が降ると発生するので、油断できません。 ゴマダラカミキリの卵が10日頃から孵化し、幼虫が幹に食い入ります。 薬剤使用の場合、高温期なので、薬害に注意して展着剤を省き、濃度も通常の1.5倍に薄めて使用するなど注意が必要です。 |
| 9月 | 上旬までに秋剪定を済ませましょう。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 1週間以上晴天が続きたら10〜15㍑与えます。特に、秋剪定の前後は3日に1回ぐらい15㍑程与えると芽の動きがよくなります。 |
| 鉢植え | 晴天であれば、毎日。 |
| 2)施肥 | 8月下旬に秋花のために施肥してあれば必要ないでしょう。 (ただし、鉢植えの場合は、肥料不足の恐れあり、液体肥料(N-P-K=6-10-5)を蕾が色つくまで、10日に1回、水やり代わりに与えた方がいいでしょう) |
| 3)HTの秋剪定 (整枝) |
8月の終わり頃から9/10までに秋剪定を済ませましょう。冬剪定と違い、よい秋花を咲かせるために行います。全体を浅めに仕上げることから整枝とも言われます。 剪定方法は専門家により諸説があり、まちまちです。例えば、①2〜3番花が咲いた枝(シュートの場合は2段目の枝)の中ほどの外側の元気な5枚葉の上5㎜〜1cmのところで切るとか、②枯れ枝、病気の枝を整理した後、残した全ての枝の先端から1/4辺りの外側の元気な5枚葉の上5mm〜1cmのところを切るなど。秋花のために葉を多く残すようにするのがポイントでしょう。 秋剪定は太い枝を切るのは避けた方がよいので、2番花が咲いた枝の直径が1cm以上であれば1段上の3番花が咲いた枝で切ります。 なお、つるバラは秋剪定をしません! |
| 4)病虫害対策 | 乾燥するとハダニが広がるので、ニッソランVの1000倍液やダニトロンフロアブル1000倍液で退治します。 |
| 10月 | 上旬には蕾もふくらみ、中旬には花が咲き始める。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 開花中はできるだけ水やりした方が花が大きく育ちます。 晴天が続けば3日おきくらいに与えます。 |
| 鉢植え | 晴天であれば2〜3日に1回。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 必要ありません。 |
| 鉢植え | 肥料が足りない恐れがありますので、蕾が色つくまでの間、液体肥料(N-P-K=6-10-5)を10日に1回程度与えた方がいいでしょう。 |
| 3)病虫害対策 | 気温が下がり、雨が多くなると黒点病やうどんこ病が多くなります。 アブラムシなども発生します。 |
| 11月 | 月末まで開花が続く。花は花首から摘んで、少しでもたくさんの葉を残しましょう。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 晴天が20日も続けば10〜15㍑程与えます。 |
| 鉢植え | 3〜5日おきに与えます。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 秋の花が終わったらお礼肥として有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各100g混合した計400g程度与えます。 なお、生育の悪い株や病気で葉が少なくなった株には枝を充実させるため、カリ分の多い液体肥料(N-P-K=6.5-6-19)を2〜3リットル水やり代わりに1〜2回与えます。 |
| 鉢植え | 秋の花が終わったらお礼肥として化成肥料(N-P-K=10-10-10)10粒を与えます。 なお、生育の悪い株には露地植え同様、上記液体肥料を液体肥料(N-P-K=6.5-6-19)を水やり代わりに1〜2回与えます。 |
| 3)病虫害対策 | 気温の低下とともにうどんこ病が多発します。 害虫は少なくなります。 |
| 12月 | 大苗の植え付け、植え替え、移植の最適期。 |
| 1)水やり | |
| 露地植え | 芽が休眠するので、必要ありません。ただし、植え付けた大苗は植え付けた後、1週間程雨が降らなければ15㍑程与えます。 |
| 鉢植え | 晴天が続けば、芽が休眠していても必要で、5〜7日に1回。 |
| 2)施肥 | |
| 露地植え | 元肥の最適期は1月ですので、必要ありません。 |
| 鉢植え | 土替え最適期の12月に土替えすのならその際、元肥をします。 肥料は有機質肥料の①油粕(主に窒素分)、②骨粉又は過リン酸石灰(主にリン酸分)、③草木灰(主にカリ分)、④熔成リン肥を各同量混合したものを10号鉢ならスプーン(大)3杯(45g程度)を鉢の3箇所におきます。 化成肥料を使う場合は、マグァンプKなど緩効性化成肥料(N-P-K=6-40-6)で代用していいでしょう。 |
| 3)つるバラの冬 の剪定と誘引 |
|
| 剪定 | 今月から1月に剪定と誘引作業を済ませます。 今年、新しく伸びた枝(シュート)は来年に花を咲かせるので、今年の新しい枝を中心に残すようにして、 葉を全て取り、枯れた枝や細い枝を取り除き、剪定します。 ①今年の年の新しいシュートは先端を20〜30cm程切り詰めます、②昨年のシュートはよい花枝が伸びないようなら切り捨てます、③シュートの途中から伸びた枝(サイドシュート)は残し、その先のシュートは切り捨てるとともにサイドシュートの先端も20〜30cm切り詰めます、④昨年のシュートか ら横枝が出て、それに開花した枝は芽を2つから3つ残して、その上5〜10mmのところを芽に平行に切ります。 |
| 誘引 | シュートを直立させておくと、上のほうに花が咲くだけで、下の方には花が付かないので、誘引は、シュートを水平にすることにより全体に花を咲かせるために行う作業です。新しい今年のシュートを下に、昨年のシュートを上にして枝と枝との間隔は30cm程あけ、誘引します。 |
| 4)つるバラの移 植 |
移植は大苗の植え付けと同じで、休眠期にあたる12月(最適期)から2月に行います。 根の量を参考にして枝の剪定に入ります。枝の総量は従前の1/3〜1/4の量まで剪定し、、残す枝は細い枝などを切り捨て、堅く充実した新しい枝を中心に残し、残す枝の枝の長さも従前の1/3まで切り詰めます。 剪定が終わったら、大苗の植え付けと同じように根の先端を軽く切り、水に浸して十分吸水させてから植え付けます。元肥は有機質肥料500gぐらいを土に混ぜ施します。 |
| 5)病虫害対策 | 病気になった葉を摘み取る程度でいいでしょう。 |
(注)「バラ」(藤岡友宏著)、「つるバラ」(村田晴夫著)、
「バラの育て方」(浜崎雅子著)、(有)イタミ・ローズ・
ガーデン発行のカタログを参考にしてまとめました。