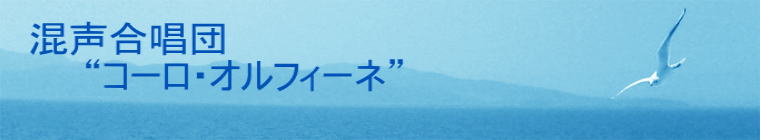
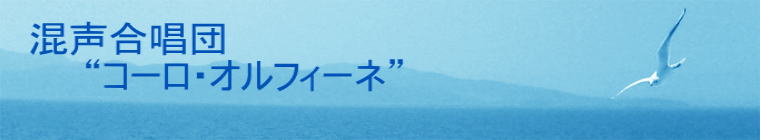 |
|
練習記録 2025年6月から 11月15日(土) 新宿文化センタ-第2会議室で久保先生の指導による練習でした。 Sop.4名、Alt.2名、Ten.5名、Bass.4名の参加でした。 発声練習をした後、コンコーネ36番の練習をしました。 細かいところの歌い方の指導を受けました。 全体で歌った後、中声用でアルトとバスが合わせて練習しました。 続いて、ソプラノとテノールで高声用で練習しました。 合唱の練習はラター“Gloria”(3)から始めました。 最後まで歌いきるには、かなりハードな曲です。 最後まできちんと歌いきれるように少し抜くところも考えていかないといけない と思います。 その1つとして、pやmpの部分は音量も声を体力も考えて抑制することも大切だと思いました。 続いて(2)の練習をしました。 最初はppでテノールはファルセットで歌うように指示されました。 中盤からのアカペラ部分は、まだまだピアノで弾いてもらってやっと歌えるとい う所なので練習が必要だと思います。 次に、鉄道組曲2番「岩手軽便鉄道の一月」を練習しました。 始めて歌う人にはリズムや音程に難しさを感じることだと思います。 だんだんに、音楽記号にも注意を向けて歌えるようにしたいものです。 最後にGloriaの(2)(3)を通して歌いました。 だいぶ分かってきたとように思いますが、声が最後まで保てないのでハーモニー が崩れているように思います。 お互い良く聴き合って良いハーモニーを保てるよ うに歌えると最後まで音が充実したものになるのではないかと思います。 11月 8日(土) 美佐先生の指導による練習。会場は、戸塚ゼフィロ。 Sop.3名、Alt.3名、Ten.4名、Bass.5名の参加でした。 発声をした後、コンコーネ36番の練習をしました。 ブレスを全員で合わせるように、全音版のブレスの位置を確認してから歌いまし た。 スラーやディミネンドなどの細かく楽譜を見て歌うようにすること。 短調から長調に代わるところをきちんと意識して歌うこと、 等を確認し合いました。 合唱の練習はラター“Gloria”(3)の音を確認していきました。 1度止まらずに最初から最後まで歌ってから、音が不確かなところを確認してい きました。 練習番号27からの“Amen”の部分が特に4/4、3/8、5/8と 変わっていくところで合わなくなってしまっていました。 5拍子になったところは、5拍目、5音目に“en”と入れると6拍子のようにな りがち、5拍目に“n”と入れるとテンポがずれにくいと女声から指摘されまし た。 最初から最後まで確認していった後に、最初から通して歌いました。 テノールまだ練習番号27からの部分があやしかったです。 個人練習をしてから次回の久保先生の練習に参加しましょう。 次にGloria(2)を確認していきました。 練習番号18からアカペラのところは、音の確認後ピアノを付けずに歌おうとし ましたが、うまくいきませんでした。 要注意箇所です。 最後に鉄道組曲2番「岩手軽便鉄道の一月」を最初から音取りをしました。 以前やったことがあるということもあると思いますが、予習をしてから練習に参 加している人が多かったようで、長い曲ですが最後まで音取りを終えました。 練習後1番「でんしゃはうたう」の歌う部分を各パートで確認しました。 今日は、効率よく練習ができたように思います。 次週15日は、久保先生による練習です。今日確認した曲の不確かなところをな るべく少なくしてから練習に参加したいものです。 10月25日(土) 新宿文化センタ-第2会議室で久保先生による指導でした。 Sop.3名、Alt.2名、Ten.4名(最後の30分+1名)、Bass.3名の参加でした。 女声の集まりが悪かったこともあり、黒人霊歌の男声曲“Swing Low”の音取り練習をしました。 続いて、鉄道組曲6番「恋の山手線」の練習をしました。 次は、鉄道組曲3番「間奏曲」と4番「上野ステーション」の音取り練習をしました。 最後に“Swing Low”を通して歌って終了しました。 10月11日(土) 新宿文化センタ-第2会議室で久保先生による指導でした。 Sop.4名、Alt.3名、Ten.5名、Bass.4名の参加でした。 発声練習はハミングの練習からでした。大きな声を出すのではなく、響きを付けることを大切に声を出すようにという指導がありました。 コンコーネは35番の練習をしました。 全体で歌った後、バス、アルトの順で中声用で歌い、続いてテノール、ソプラノの順に高声用で練習しました。 装飾音符などまだまだという気がしますが、先生に36番へ進めるのかどうか聞くのを忘れてしまいました。 合唱は ラター“Gloria”(1)を練習した後に、(2)の音取りをしました。 パートが分かれるところやぶつかり合うところの音程がまだまだというところだと思います。 (1)とともに(2)も音取り用音源をアップしてくださいましたので、参考にして次回練習へ繋げていきたいと思います。 最後に、“Da Battle of Jerico”を歌って終了しました。 10月 4日(土) 美佐先生の指導による練習。会場は、スタジオ・アンダンティーノ。 Sop.4名、Alt.3名、Ten.4名、Bass.2名の参加でした。 コンコーネ35番と36番の練習をしました。 鉄道組曲6番「恋の山手線」の音取り練習をしました。 P169、以前買った楽譜では「しながわ、たばたに、はままつちょう」となっていましたが、「しながわ、たまちに、はままつちょう」と新版ではなっているということで、山手線の順でいえば「田町」が正しいので旧版の変更をしました。(なぜ気が付かなかったのでしょう?) ゆっくりと練習すると音を間違って歌っているところが見つかりました。 山手線は最後まで音取りをして最後に通して歌いました。 次にラター“Gloria”(1)を通して歌って終了しました。 9月27日(土) 久保先生による指導で、豊洲文化センター音楽室で行いました。 Sop.3名、Alt.5名、Ten.5名、Bass.5名の参加でした。 発声練習では、バスの低い音を出すところから練習をする。体を大きく開いて出 す。高い音を出す時に目の後ろの空間を大きく開いて出すことを心がける。 「アエイオウ」で母音の音色を変えないように声を出す練習。各パートごとにも 練習しましたので、良くなったところを身につけていきたいものです。 コンコーネは34番を練習。 全員で歌って音を確認した後、 アルト、バス、テノール、ソプラノの順番に練習。 次回の先生練習で35番を歌います。 自主練習で練習しますが、自主練習をして参加しましょう。 合唱練習は、本日手元に届いたラター“Gloria”(1)の部分の音取りをしまし た。 平野先生の指導で歌った曲ですが、ほとんど覚えていない感じで進められていきました。。 次回は、自主練習を行いますが、「鉄道組曲」も揃ったので、“Gloria”と2冊 持ってきた方が良いと思います。 9月13日(土) 久保先生による指導。豊洲文化センター音楽室で行った。 Sop.3名、Alt.4名、Ten.4名、Bass.4名の参加だった。 発声練習では、高い音を出す時に口を横に開いて出さないように、縦に広げて出すようにする。 コンコーネは33番を練習した。 パートの音を揃えることを目的にパートごとに練習しました。お互いの音を良く聴くように指示された。 バスは、高音の部分を出す前に準備をしてから頭に声を回すように出すように。 アルトは鼻の上の部分をもっと上げ、声をその部分に当てるように出す。 低い音を出す時も響きを内声パートなのできちんと聞こえるようにするためには、低い音でも下顎の力を抜いて響きをもう少し上に持っていくようにすると良い。 ソプラノは声質を揃えるために、“La”で歌いました。“L”で声をはじくように練習した。高い音でビブラートの波形が下に付かないように気をつけること。 テノールは高い音で生声にならないように上に回すことをもっと意識して出すように指導された。 次回の先生練習で34番を歌います。自主練習で練習していませんので自分練習 をして参加したいものだ。 合唱練習 1曲目は、前回の自主練習で音取りをした“Didn't my Lord deliver Daniel”を練習した。 音をかしこまってきちんと歌うのではなく言葉をしっかりと語るように歌うことも大切。 2曲目は、“Nobody Knows” の合唱部分だ練習していった。 残りの時間で、2曲を通して歌って終了した。 黒人霊歌は歌うための体力も集中力もかなり必要だと感じる。 9月 6日(土) 美佐先生による指導。 Sop.3名、Alt.2名、Ten.4名、Bass.5名の参加。 K夫妻の参加により Sop.4名、Alt.5名、Ten.6名、Bass.5名 合計20名になったと思う。 北新宿生涯学習館・視聴覚室での練習だった。 発声練習の後、コンコーネは33番を練習した。 全員で中声用、テノール−とソプラノは高声用での練習もした。 次回の先生練習で32番を歌います。しっかり歌えるように練習して参加したいもの。 合唱練習 1曲目は、前回の自主練習で途中まで音取りをした“Didn't my Lord deliver Daniel”を練習した。 2曲目は、“Nobody Knows” の合唱部分だけ音取りをした。 3曲目は、“Da Battle of Jerico1984年版”の復習した。 次に、“Nobody Knows”にソロを付けて練習した。 最後に“Steal Away”を練習して終了。 これで黒人霊歌の混声曲については8曲とも音取りが終了したことになる。 どの曲を練習するとことになっても、すぐに歌えるようにしたいものだと思う。 8月23日(土) 久保先生による指導。 Sop.4名、Alt.4名、Ten.5名、Bass.5名の18名参加で した。アメリカの仕事を終えて帰国されたご夫婦の参加がありました。 新宿区西戸山学習館・視聴覚室での練習でした。 発声練習では、巻き舌で高音まで歌って舌根に力が入らない状態で声を出す練習 をしました。 コンコーネは32番を練習しました。 バスとアルトで中声用、テノール-とソプラノで高声用で練習しました。 どこをどのように歌えばよいのか細かいところまで指導していただきました。 次回は33番を練習とのことです。 合唱練習は、 1曲目は、前回自主練習で音取りをした“Rocka My Steal Away” 2曲目は“Dry Born”を練習しました。 3曲目には1984年版の“Da Battle of Jerico”を練習しました。 前回まで練習していたところと音が違うところを確認しました。 最後に4曲目“Steal away”を練習して終了しました。 演奏家に向けての曲は、 益田先生編曲の“Spiritual” 信長貴富作曲 “鉄道組曲”全曲 の再演 ラター“Gloria”を練習していくことになりました。 8月 9日(土) 伊藤美佐先生による指導。 Sop.3名、Alt.2名、Ten.4名、Bass.4名の参加。 西戸山生涯学習館視聴覚室での練習だった。 発声練習の後、コンコーネは32番を練習した。 バスとアルトで中声用、テノール-とソプラノは高声用での練習もした。 次回の先生練習で32番を歌う予定。しっかり歌えるように練習して参加したいものだ。 合唱練習は、 1曲目は、“Dry Born” 2曲目は、“Rocka My Soul” の音取りをしました。 3曲目は、“Didn't my Lord deliver Daniel”は時間がなく途中までの音取りで終わった。 最後に1回“Dry Born”を通して歌って終了した。 8月 2日(土) 久保先生による指導。Sop.2名、Alt.3名、Ten.5名、Bass.5名の参加。 男声は全員参加。 住吉生涯学習館レクホールでの練習だった。 発声練習の後、コンコーネは31番を練習した。 バスとアルトで中声用、テノール-とソプラノで高声用で練習した。 細かいところまで指導していただいた。 次回は32番を練習とのこと。 合唱練習は、 1曲目は、“Steal away” 2曲目は、“Da Battle of Jerico” 3曲目は、“Deep river” 4曲目は、“Were you there When they crucified my Lord” の練習をした。 最後に、“Deep river”のソロ部分の練習をして終了した。 7月19日(土) 久保先生による指導。Sop.2名、Alt.2名、Ten.4名、Bass.4名の参加。 戸山生涯学習館ホールでの練習だった。広い会場でしたが、ピアノの調律が悪かったのが残念。 発声練習の後、コンコーネは30番をバスとアルトで中声用、テノール-とソプラノで高声用で練習した。音の幅があるところや半音を正確に取る練習をした。 次回、8月2日は31番の練習する予定です。 合唱練習は、前回までの自主練習で音を取っていたものを練習していった。 言葉については、久保先生がアメリカで黒人の先生に師事していたということで、分からないところをお聞きすると統一した発音になることが分かってよかった。 1曲目は、“Steal away” “got”は「ガットゥ」、“here”は「ヒー」の最後に「ア」と軽く言うけれど強調しない。「ヒー」だけで良い感じだった。 2曲目は、“Da Battle of Jerico”の練習をした。 31小節テノールの音は、55小節と同じにすることにした。 言葉のアクセントを大切に歌うように指導された。 3曲目は、“Were you there When they crucified my Lord” “crucified”の“ci”は「スィ」と発音することで統一された。 ソロを付けるに、合唱パートの練習をした。 4曲目は、“Deep river”この曲も主にソロ無しで合唱部分の練習をした。 5曲目は、“Wade in de Water” この曲と“Swing low”は男声版の編曲なので男声で音を取り直していくことになった。 “Water”の“a”は深い「あ」で歌うようにと指導された。 残りの時間で練習した曲は最初から歌った。 7月12日(土) 伊藤先生の指導による自主練習。ゼフィロで行った。 Sop.2名、Alt.4名、Ten.3名、Bass.5名の参加。 発声練習で、半音を正確に取る練習をした。 コンコーネは30番を復習した後に、31番の音取りをした。 30番は19日の先生練習の時までにしっかりと間違えないで歌えるようになっ ていきたい。 31番は8月2日に練習する予定。 合唱練習は、前回練習した“Da Battle of Jerico”の復習から行った。 第4回益田先生の最後の演奏会では、古いバージョンで歌っていた。 古いバージョンを残したいと思ったのだろうか? 次に新しい曲として “Wade in de Water”と“Were you there When they crucified my Lord”の音 取りをしました。 『Water』は「ワーター」と発音と統一したが、活字を見ると「ウォーター」 と発音してしまっていることが多かったので注意したい。 しかし、YouTubeを聴いてみると、「ワーター」と言っているものもあるが「ウォーター」寄りの発音をしている参考にした可能性がある『ゴールデン・ゲート・カルテット」は「ウォーター」と発音している。 残りの時間で、“Steal away”と“Deep river”を1度復習で歌ってみて終了した。 7月 5日(土) 伊藤美佐先生の指導による練習。 新宿区にある北新宿生涯学習館で始めて行う。 学習室A70㎡ほどでアップライトピアノ。ただ、床に固定されていて動かせないのが難点。 発声練習で、1音の幅を正確に取る練習。 和音の練習など音を正確に出したり、聴き合ったりすることを意識して声を出すことをしていった。 コンコーネ30番は全員歌った後バスとアルト、テノールとソプラノで練習した。 音の動きに付いていけないところ、16分音符のところで音符の長さが正確に歌えないところなど練習した。 19日の先生練習の時までにしっかりと間違えないで歌えるようになっておきたいところだ。 合唱練習は、前回練習した“Steal away”の復習から行った。 かなり聴き合って良いハーモニーになったところもありましたが、最後に通して歌うとところどころぶれているところがあった。 発音ですが“got”は「ゴット」ではなく、「ガット」“here”は「ヒー」でいいようだ。 続いて “Da Battle of Jerico”を練習番号で区切りながら音取りをした。自分の音を正しく歌えるようにするという段階だが、他のパートがどんな曲なのかを音取りの時から聴いておいて合わせて歌う時に参考にしていくことが大切だと思う。メロディパートがどこかも捉えて歌うことも考えていきたい。 次回も、自主練習。 6月14日(土) 久保先生による指導。 コンコーネ30番の練習の後、黒人霊歌“Steal away”と“Deep River”の音取り練習をしたそうだ。 2025年6月1日(日) 最初に発声練習とコンコーネ29番(一度歌ったことがあった)を歌う。 その後、今回の演奏会について話し合った。 先生、リサイタル委員長、印刷担当の順に話してもらう。 聴きに来ていただいた方からも先生からも高評価をいただいた。 今後については、会費を貯金がある内は月に5000円にする。 都内の会場を探していく。など その後選曲を行ったが。 益田先生の作品(黒人霊歌)、日本語の曲、ラテン語の曲の3部構成にすることに決めた。 黒人霊歌を練習していくことにする。 |